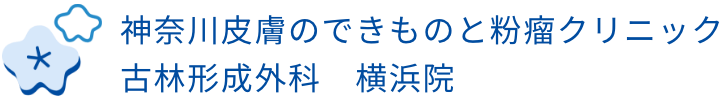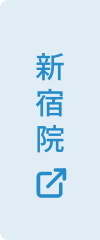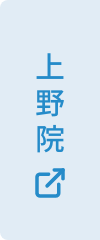急にできたほくろは危険?皮膚がんの可能性と見分け方

神奈川県横浜市の「神奈川皮膚のできものと粉瘤クリニック 古林形成外科横浜院」です。当院では、日本形成外科学会認定の形成外科専門医が、ほくろの診察・治療を行っています。
本記事では、急にできたほくろのリスクや正常なほくろとの違い、さらに皮膚がんの可能性があるほくろの特徴や見分け方について解説します。ぜひご参考ください。
急にできたほくろは危険?正常なほくろとの違い

急に新しくほくろ(医学的には「色素斑」と呼ばれる皮膚の色素沈着)ができた場合、必ずしも危険というわけではありませんが、注意が必要です。
ほくろは一般的に子どもの頃から思春期にかけて増えることが多く、大人になってから新しくできることは少数です。そのため、成人以降に突然現れたほくろや、数週間から数か月の短期間で大きくなる・色が濃くなるといった変化を示す場合には、皮膚がんの可能性を否定できません。
通常のほくろは左右対称で境界が明瞭、色も均一で直径6mm未満であることが多いのに対し、悪性の可能性があるほくろは形がいびつ、色がまだら、大きさが6mmを超える、出血やかゆみが持続するといった特徴がみられます。
特に「他のほくろと比べて明らかに異質に見える」場合は注意が必要です。もし急にできたほくろにこうした特徴があれば、自己判断せず、専門医の診察を受けることが大切です。
なぜ急にほくろができるのか|原因と仕組み

ほくろは、医学的には「色素性母斑(しきそせいぼはん)」と呼ばれる良性の皮膚腫瘍です。皮膚の中にある「メラノサイト」と呼ばれる色素細胞が集まり、「母斑細胞」へと変化してかたまりを形成することで生じます。
メラノサイトは通常、紫外線から皮膚を守るためにメラニンという色素を作り出していますが、この細胞が一部に集中すると、皮膚の表面にほくろとして現れます。子どもから思春期にかけてはホルモンの影響でほくろが増えることが多い一方、大人になってから新しくできることは多くありません。ただし、以下のような要因によって成人以降にも新しいほくろができることがあります。
紫外線の影響
長期間にわたる日光曝露はメラノサイトを刺激し、メラニンの産生や細胞の増殖を促進します。その結果、新しいほくろができることがあります。
ホルモンバランスの変化
妊娠・出産・更年期など、体内のホルモン環境が変化するとメラノサイトの活動が一時的に活発になり、ほくろができやすくなる場合があります。
加齢による変化
加齢に伴い皮膚細胞のターンオーバーや色素細胞の働きが変化することで、新しい色素斑やほくろが生じることがあります。
悪性腫瘍(皮膚がん)の可能性
「急に増えた」「大きさや形が変化した」「境界がぼやけている」といった特徴がある場合には、皮膚がんの可能性も否定できません。特に、既存のほくろと明らかに異なる外見や急激な変化がある場合には注意が必要です。
皮膚がんの可能性があるほくろの特徴

急にできたほくろの中には、悪性黒色腫(メラノーマ)など皮膚がんのリスクがあります。皮膚がんを早期に発見するためには、正常なほくろとの違いを知っておくことが大切です。その判断基準として、国際的に広く用いられているのが「ABCDEルール」です。
ABCDEルール
A(Asymmetry:左右非対称)
通常のほくろは丸く左右対称であることが多いですが、皮膚がんは形がいびつで左右非対称になります。
B(Border:境界の不明瞭さ)
正常なほくろは境界がはっきりしていますが、皮膚がんは周囲との境界がギザギザしたり、ぼやけて見えるのが特徴です。
C(Color:色の不均一)
正常なほくろは色が均一ですが、皮膚がんでは黒・茶・赤・白など複数の色が混ざってまだらに見えることがあります。
D(Diameter:大きさ)
直径6mm以上の大きなほくろは注意が必要です。小さくても急速に大きくなる場合には検査が推奨されます。
E(Evolution:変化)
短期間で大きさや色、形が変化したり、かゆみ・出血・かさぶたの形成を伴う場合は特に注意が必要です。
これらのABCDEルールに当てはまる特徴があるほくろは、皮膚がんの可能性を否定できません。特に、日本人では悪性黒色腫の一部が手のひら・足の裏・爪といった部位に発生しやすいことが知られています。
気になる症状がある場合は、自己判断せず、専門医を早めに受診することが大切です。
ほくろと皮膚がんを区別するための検査

ほくろと皮膚がんを正確に区別するには、専門的な検査が必要です。
検査では、まず医師による視診と触診が行われます。大きさや形、色調、境界の明瞭さ、盛り上がりの有無に加え、出血やかさぶたの有無などを確認します。次に、診断精度を高めるためにダーモスコピー(皮膚拡大鏡)による検査が行われます。特殊な拡大鏡を用いて皮膚表面の模様や色の分布を詳しく観察し、肉眼では見逃しやすい特徴を捉えることができます。
さらに、悪性黒色腫など皮膚がんの疑いが強い場合には、超音波検査・CT・MRIといった画像検査を行い、転移の有無を評価する場合もあります。最終的に診断を確定するためには、病変の一部または全体を切除して顕微鏡で詳しく調べる病理組織検査が必要になってきます。
まとめ|急にできたほくろは専門医に相談を

急に新しくほくろができたからといって、必ずしも危険というわけではありません。しかし、皮膚がんの可能性を完全に否定することはできないため、注意が必要です。
特に「急に数が増えた」「大きさや形が変わった」「境界が不明瞭」「色がまだら」といった特徴をもつほくろは要注意です。既存のほくろと明らかに異なる外見や、短期間で急激な変化がみられる場合には、皮膚がんのサインである可能性があります。
ほくろと皮膚がんを正確に区別するには、専門的な検査が欠かせません。皮膚がんの中には悪性度の高いタイプも存在するため、気になる症状がある場合は自己判断せず、早めに専門医を受診することが大切です。
ほくろの治療は当院へご相談ください

神奈川県横浜市の「神奈川皮膚のできものと粉瘤クリニック 古林形成外科横浜院」では、日本形成外科学会認定の形成外科専門医が、皮膚疾患に対する専門的な知見をもとに、ほくろの診断と治療を行っています。
当院では、患者さま一人ひとりの症状やご希望を丁寧にお伺いし、豊富な経験と専門知識に基づいた治療を行っています。ほくろに関する不安やお悩みがある方は、当院までお気軽にご相談ください。