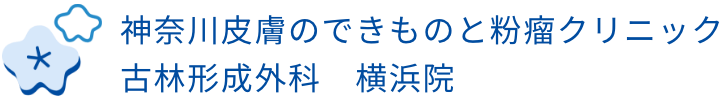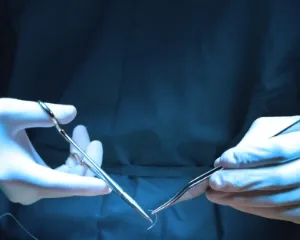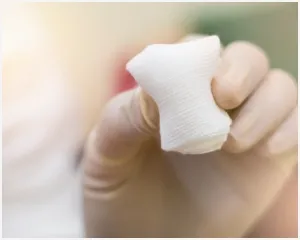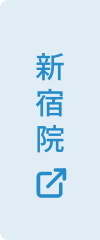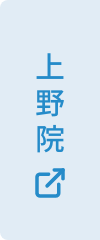眼瞼下垂の症状
私たちは1日に約2万回、1年間で約700万回ものまばたきをしています。年齢を重ねるにつれて、足腰が弱くなるのと同じように、まぶた(眼瞼)の機能も衰えていきます。腱膜性眼瞼下垂症は主に加齢による変化が原因で、長生きすれば誰でもいつかは眼瞼下垂になる可能性があります。
“まぶたの衰え”は、ある日突然起こるわけではなく、ゆっくりと進行するため非常に気づきにくいものです。まぶたが下がって見えにくくなる前に様々な症状が現れますが、これが眼瞼下垂の症状だと認識していなければ、ご自身で気づくことは難しいかもしれません。
以下は、眼瞼下垂症の主な症状です。
思いあたる症状はありませんか?
上まぶたが重く感じる、目が開けにくい
視野が狭くなった気がする
最近、周りの人から眠たそうだとよく言われる
目を開けるときに、おでこに深いシワができたり、眉毛が吊り上がったりする
何かを凝視する時に無意識に顎が上がる
慢性的な肩こりや頭痛、首の痛みがある
眼精疲労がひどい
まぶたの上がくぼんでいる
二重(ふたえ)の幅が広くなった
右目と左目で開き具合に差がある
眼瞼下垂症の初期段階では、上まぶたが重く感じられ、目が開けにくくなります。
眠たそうに見えたり、視野が狭く感じられることがあります。進行すると、まぶたが視野を妨げないようにするため、顎を上げて頭を後ろに倒すような姿勢を取ることがあります。
また、まぶたを開ける力が弱くなるため、前頭筋(ぜんとうきん)を使って眉毛とまぶた全体を持ち上げ、視野を確保しようとします。これにより、ひたいに太い横シワが入りやすくなります。
眼瞼下垂の随伴症状
ひたいの筋肉の緊張が続くと、肩こりや首こり、緊張性頭痛などが起こりやすくなります。これらの症状は、眼瞼下垂症に伴って起こる随伴症状です。まぶたにある筋肉の中には、神経受容体(周囲の変化を脳に伝えるセンサー)があります。
腱膜が緩むことで、これらの神経受容体が刺激され、そのシグナルが脳や中枢神経に伝わると、他の神経が刺激され、体内の神経のバランスが崩れることがあります。これにより、様々な随伴症状が現れることがあります。
代表的な眼瞼下垂の随伴症状には、「肩こりや頭痛」のほか、「めまい」「不眠症・入眠障害」「不安障害」「自律神経失調症」「眼瞼や表情筋の痙攣」などがあります。
眼瞼下垂の原因
上まぶたを上げ下げする動作には、動眼神経が支配する上眼瞼挙筋(じょうがんけんきょきん)と、交感神経が支配するミュラー筋(瞼板筋とも呼ばれます)が関与しています。これらの筋肉が、まぶたの芯となる構造である瞼板を引っ張り上げることで、まぶたが開きます。
筋肉と瞼板は腱膜という組織で繋がっており、この腱膜がたるんでくると、筋肉の力が瞼板に効果的に伝わらなくなり、まぶたが上がりにくくなってしまいます。多くの眼瞼下垂は、このようなメカニズムで発生します。加えて、皮膚のたるみや筋肉の衰えも、眼瞼下垂の要因となることがあります。
眼瞼下垂には、「先天性眼瞼下垂」と「後天性眼瞼下垂」の2つの種類があります。先天性眼瞼下垂は、生まれつきまぶたが下がっている状態を指し、一方で後天性眼瞼下垂は、もともと正常に開いていたまぶたが徐々に下がってくる状態です。
後天性眼瞼下垂の原因として最も多いのは加齢ですが、ハードコンタクトレンズの長期使用や、白内障手術などの手術歴がある方にも生じることがあります。
先天性眼瞼下垂
先天性眼瞼下垂は、出生直後から見られる生まれつきの眼瞼下垂であり、まぶたを持ち上げる上眼瞼挙筋の形成不全や、これを動かす神経の発達異常が原因とされています。片側性と両側性があり、片側性が約8割を占めます。
下垂のある目は下方しか物が見えないため、これを補おうとして、顎を上げた姿勢で物を見るようになったり、眉毛を上げて目を開けるようになったりすることがあります。眼瞼下垂の程度が強い場合、視力の発達に影響を及ぼすこともあります。
また、まれに交感神経系の疾患であるホルネル症候群が原因で眼瞼下垂が生じることもあります。ホルネル症候群は、目と脳を結ぶ神経線維が分断されることによって引き起こされる疾患で、片側のまぶたが垂れ下がるだけでなく、瞳孔の収縮、虹彩の色素異常、顔面の発汗低下(異常がある側)などが同時に見られます。ホルネル症候群には、先天性だけでなく後天性のものもあります。
ハードコンタクトレンズの長期使用
コンタクトレンズが原因で眼瞼下垂を引き起こすケースは、ソフトレンズよりもハードレンズを使用している方に多く見られます。特にハードレンズを10年以上使用している方では、高い確率で眼瞼下垂の症状が現れることがわかっています。
一般的に、瞬きの回数は1日15,000~20,000回とされていますが、ハードレンズという硬い異物を目に装着したまままばたきを繰り返すことで、長期間の使用を続けていると、上まぶたを支えている挙筋腱膜やミュラー筋の収縮力が低下し、まぶたが下がりやすくなると考えられています。
さらに、レンズの取り外しの際に、過度にまぶたを引っ張ることも眼瞼下垂の要因の一つとされています。コンタクトレンズによる眼瞼下垂は、片側のまぶただけ下垂が顕著に進むことが多く、これによって目の左右差が目立ち、悩まれる方も少なくありません。
加齢
年齢を重ねると、足腰が弱くなるのと同じように、まぶたの機能も徐々に衰えていきます。
まぶたを引き上げる際に重要な役割を果たす「腱膜」と「瞼板」がしっかりと結びついていると、挙筋の力は100%瞼板に伝わり、まぶたが容易に上がります。しかし、加齢に伴い、腱膜と瞼板の結合が緩んだり、挙筋腱膜自体が弱くなったりすることで、力がうまく伝わらなくなります。最終的に結合が外れてしまうと、挙筋の力ではまぶたを上げることができなくなります。
このような状態を「腱膜性眼瞼下垂」といい、多くの場合、加齢が主な原因であり、数年かけて徐々にまぶたが下がってくることが特徴です。また、加齢によるまぶたの皮膚のたるみも、まぶたの開きを妨げる要因となります。
内眼手術の既往
白内障手術、緑内障手術、硝子体手術などの内眼手術を受けた方にも、眼瞼下垂が生じることがあります。
内眼手術中は、まぶたが閉じないように開瞼器(かいけんき)という器具を使用します。この開瞼器でまぶたを広げた状態が、手術の間中続きます。長時間にわたり、まぶたを強制的に開かせるため、この過程で眼瞼挙筋や腱膜にダメージが加わり、結果的に眼瞼下垂が発生することがあります。
神経麻痺や筋肉の疾患
まれに、神経麻痺や筋肉の病気が原因で眼瞼下垂が生じることもあります。
脳動脈瘤や糖尿病による動眼神経麻痺、肺がんなどに伴う交感神経麻痺、神経と筋肉の接合部分に異常が生じる重症筋無力症などが該当します。
これらの場合、眼瞼下垂以外にも目の症状や全身の症状が現れることが多く、まずはこれらの疾患に対する治療が優先されます。
眼瞼下垂の手術
眼瞼下垂症の手術には、主に挙筋前転術(きょきんぜんてんじゅつ)や挙筋短縮術(きょきんたんしゅくじゅつ)、眼瞼皮膚切除術(がんけんひふせつじょじゅつ)、そして前頭筋吊り上げ術(ぜんとうきんつりあげじゅつ)といった方法があります。
これらの手術は、患者様の状態に合わせて適切な方法が検討されます。
挙筋前転術(または挙筋短縮術)
挙筋前転術(または挙筋短縮術)は、収縮力が低下した挙筋腱膜(きょきんけんまく)を縮めて修復し、まぶたを引き上げる手術です。主に、上眼瞼挙筋と瞼板(けんばん)の間にある腱膜が伸びている場合に行われます。
挙筋前転術では、上まぶたの皮膚を切開し、たるんだ腱膜や筋肉を前方に引っ張り、細いナイロン糸で瞼板に縫い付けて短縮します。挙筋短縮術では、伸びてしまった腱膜を一度瞼板から剥がし、腱膜の一部分を短く切除した後、再び瞼板に縫い付けます。
これらの手術により、腱膜のたるみが改善され、上眼瞼挙筋の力が瞼板にしっかりと伝わるようになるため、まぶたがしっかりと開くようになります。なお、まぶたの皮膚が弛緩してたるんでいる場合は、皮膚切除術を併せて行うこともあります。
眼瞼皮膚切除術
眼瞼皮膚切除術は、まぶたがたるんで余分な皮膚が生じた場合に、それを切除して垂れ下がりを改善する手術です。まぶたを上げるための上眼瞼挙筋や腱膜が正常に機能していても、皮膚のたるみが強く、下垂が見られる場合に行われます。この手術には、二重(ふたえ)形成のためにまぶたの皮膚を切除する方法や、緩んだ皮膚を眉毛の下で切除する「眉下切開」の方法があります。
前頭筋吊り上げ術
前頭筋吊り上げ術は、上眼瞼挙筋腱膜自体の機能低下が顕著で、挙筋前転術などの手術では改善が難しい重度の眼瞼下垂に対して行われます。
この手術では、前頭筋(おでこの筋肉)を利用してまぶたを引き上げます。手術では、眉毛の上とまつ毛の上の2カ所を切開し、まぶたの皮下に紐を移植し、ひたい部分にある前頭筋とまぶたを連結します。
移植する紐は通常、大腿部(ふともも)から採取した筋膜を紐状に加工して用いられます。前頭筋が眉毛を上下させる動きが、この紐を介してまぶたに伝わり、まぶたを開閉できるようになります。
保険適用による眼瞼下垂手術
当院では、保険診療による眼瞼下垂手術を行っており、美容目的の手術は実施しておりません。
治療の対象となるのは、まぶたが瞳にかかることで視力低下や視野狭窄など、機能的な障害を引き起こしている患者様です。
保険適用が可能となる主な症状には、以下のようなものがあります。
まぶたが下がって視界が狭い
上の方や横の方が見にくい
テレビや本を見ているとまぶたが垂れてくるので手で持ち上げている
おでこや頭に力が入って頭痛や肩こりが取れない
まつ毛が視界に被さって見にくい、あるいはまつ毛が目に入る など
眼瞼下垂の手術内容や症状について、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
当院の眼瞼下垂手術の特徴
日帰りで行う眼瞼下垂手術
眼瞼下垂手術は、まぶたに対する局所麻酔のみで行い、手術時間も20〜30分程度で終了するため、日帰りで受けていただけます。手術翌日から運転や事務仕事なども可能で、仕事や生活への影響を最小限に抑えた負担の少ない手術です。
局所麻酔の痛みへの配慮
局所麻酔の痛みをできる限り軽減するために、極細針を採用し、麻酔薬にも工夫を施しています。
極細針に加え、こうした麻酔薬の工夫により、麻酔注入時の痛みを軽減しています。また、切開部には髪の毛よりも細い糸を使用し、丁寧に縫合を行います。
手術後の綺麗な仕上がりだけでなく、患者様の痛みを最小限に抑えることを目指しています。
当院の麻酔薬の工夫
麻酔薬は中性に近いほど痛みが軽減されます。
一般的に、局所麻酔薬には1%もしくは0.5%のエピネフリンを配合したキシロカインが用いられますが、この場合、薬剤は酸性(pH3.5~5)に偏ってしまいます。そのため、当院では局所麻酔薬に7%のメイロンを混ぜて中性(pH7)に近づけることで、麻酔注入時の痛みを軽減しています。
傷あとが目立ちにくく綺麗な仕上げ
形成外科は、手術による傷あとを目立ちにくく、綺麗に仕上げることを得意とする診療科です。
当院では、第一線で活躍してきた日本形成外科学会認定の形成外科専門医が、患者様の状態に最適な手法を選択し、細やかな配慮をもって丁寧に手術を行います。診察においても、執刀医が詳しくご説明いたします。
負担の少ない日帰り手術とはいえ、手術に対して不安や疑問を抱かれることもあるかと思います。少しでも心配なことや気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。