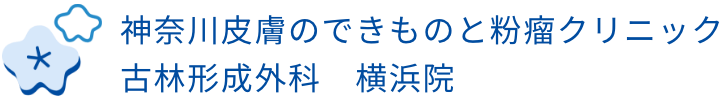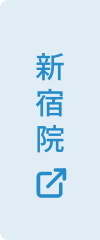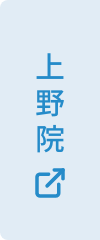皮膚がんとは
「皮膚がん」とは、皮膚にできる悪性腫瘍の総称であり、これらの手術治療は形成外科の手技の一つに含まれます。主な皮膚がんには、「基底細胞がん」「有棘細胞がん(扁平表皮がん)」「悪性黒色腫(メラノーマ)」などがあり、比較的おとなしい性質のものから悪性度の高いものまでさまざまです。
皮膚がんは、内臓のがんと違って目で見えるため、ご自身でも比較的早期に発見しやすいです。そのため、どのような見た目のものが皮膚がんの可能性があるのか、あるいはどのタイミングで医療機関を受診すべきかを知っておくことはとても大切です。ここでは、代表的な皮膚がんについて、良性・悪性の見分け方の基本や治療法について解説します。
良性・悪性の見分け方の基本
皮膚がんは、イボのように盛り上がったもの、シミのように平らなもの、湿疹のように赤く腫れているもの、ほくろのようなものなど、さまざまな形態があります。良性か悪性かを見分ける基本的な方法には、「硬さ」や「表面」の観察があります。
硬さ
悪性の腫瘍は硬く、でこぼこした感触であることが多いです。また、がんが周りの組織に癒着しているため、押してもあまり動かないことが特徴です。
一方、良性の腫瘍は柔らかく、表面はなだらかに丸みを帯びています。良性腫瘍の内容物は周囲の組織と独立しているため、押してみるとコリコリと動きます。
表面
表面の特徴としては、出血する、ジクジクしている、周囲との境界が不鮮明、かさぶたがある、などが挙げられます。ただし、これらの特徴がなくても悪性の場合もあります。
完全に見極める方法は?
医学的な診断をしなければ、良性と悪性を完全に見極めることはできません。最終的には必ず専門医による診察が必要です。
皮膚がんの治療は外科的切除が主ですが、診断目的でダーモスコピーという拡大鏡を用いたり、リンパ節や他臓器への転移が疑われる場合には、超音波、CT、MRIなどの画像検査を行うこともあります。また、腫瘍の一部を採取し、病理検査で確定診断を行ってから手術を行う場合もあります。これらの検査がすべて必要になるわけではありませんが、適切な治療を行うために、このような検査を受けていただく場合があります。
しかし、一般的には、できものができたからといってすぐに医療機関に行くほど、できものに対する病気の意識は高くないのが現状です。そこで、次に医療機関を受診する際の判断材料として、代表的な皮膚がんの特徴をご紹介します。
代表的な皮膚がんの種類とその特徴
皮膚には表皮と真皮があり、外気と接する表皮は、体表面を覆って細菌などの異物が侵入することを防ぎます。古くなると垢として剥がれ、細胞が盛んに増殖することで常に新しい表皮を生成しています。その下層にあるのが真皮です。ここには、栄養を運ぶ血管やリンパ管、痛みや温度を感じる神経が分布しています。その下には、皮下脂肪、筋肉、骨という構造が続きます。
皮膚がんは、真皮にできることはほとんどなく、多くは表皮にある有棘細胞や基底細胞ががん化することで発生します。また、ほくろのもとになる色素細胞ががん化すると、ほくろのがんとも呼ばれる悪性黒色腫(メラノーマ)になります。これらの「表皮細胞のがん」と「悪性黒色腫」が、皮膚がんの中心的な種類です。
基底細胞がん
基底細胞がんは、表皮の最も深い層にある基底細胞や、皮膚の内側で毛を包み込んでいる毛包の細胞から発生すると考えられています。日本人に最も多くみられる皮膚がんで、高齢者の頭皮や顔(頬、上下のまぶた、鼻、上口唇の周り)に好発します。
黒色から灰黒色のほくろによく似たぶつぶつとした盛り上がりで、表面にはつややかな光沢があります。数年かけて徐々に大きくなり、中心部がへこんで潰瘍をつくり、周辺部は堤防状に盛り上がってきます。通常、痛みやかゆみなどの自覚症状はありません。
リンパ節や内臓に転移することは極めてまれですが、放置すると周りの正常組織を破壊しながら増殖し、筋肉や骨などの深い組織へと浸潤することがあります。特に皮下脂肪の少ない顔面では深部まで浸潤しやすく、骨を崩してしまうこともあります。
治療は手術による切除が主ですが、確実に切除しないと同じ箇所で再発(局所再発)することがあるため、初回の手術でしっかりと取りきることが大切です。基底細胞がんは日光(紫外線)曝露が原因で引き起こされることが多いため、予防として紫外線対策を行うことも有効です。
有棘細胞がん(扁平上皮がん)
有棘細胞がんは扁平上皮がんとも呼ばれ、基底細胞がんに次いで日本人に多い皮膚がんです。これは、表皮の有棘層を構成する細胞が悪性化した腫瘍であり、盛り上がったしこりとして現れるため、イボと誤認されることがあります。高齢者に好発しやすく、頭皮や顔(鼻、耳、唇、まぶた)、手の甲などに生じることが多いです。また、やけどのあとや傷あと(瘢痕)に発症することも少なくありません。
原因としては、紫外線の影響や、子宮頸がんの発症誘因としても知られるヒトパピローマウイルス(HPV)の関与が注目されています。その他にも、放射線治療後に起こる慢性放射線皮膚炎が挙げられます。また、前癌病変である日光角化症やBowen(ボーエン)病から有棘細胞がんに変化することもあります。
症状としては、皮膚の一部が赤くなり、イボのようなしこりが形成されます。びらんやえぐれた腫瘍になると、ジュクジュクした赤い盛り上がりに見え、出血したり、角化性結節が形成されてかさぶた状態や硬化が生じることがあります。進行すると、腫瘤から体液が染み出し、独特の悪臭を放つこともあります。自覚症状はないことが多いですが、神経浸潤が起こると強い疼痛が伴います。
早期発見できれば、治癒する可能性が高い皮膚がんですが、リンパ節などに転移する可能性もあるため、気になる症状がある場合は、早急に受診してご相談ください。
有棘細胞がんが疑われる所見
- 表面がジュクジュクしていたり、かさぶた状態になったりしている
- できものを繰り返している場所にできている
- 悪臭がある
- 顔面や手の甲など、紫外線を浴びやすい部位にできている
前癌病変について
赤くなる皮膚がんには、有棘細胞がんとその類症があります。いずれも表皮を構成する角化細胞から発症するがんであり、類症としては「日光角化症」や湿疹と誤認されやすい「Bowen(ボーエン)病」があります。これらは前癌病変とも呼ばれ、放置すると有棘細胞がんに移行する可能性があるため注意が必要です。
日光角化症
日光角化症は、長期的に日光(紫外線)を浴び続けることによって発症する前癌病変で、高齢者の頭皮、顔、手の甲などに起こりやすいため「老人性角化症」とも呼ばれています。仕事や趣味で長時間屋外で過ごし、日焼けを繰り返している人や、日焼けで皮膚が赤くなる色白の人に生じやすい傾向があります。
臨床症状により、病型が分類されています。最も多く見られるのは紅斑(赤み)型で、数ミリから2センチ程度の赤っぽいシミのようなカサカサとした状態が特徴です。かゆみや痛みなどの自覚症状はなく、境界が不明瞭で、数カ月以上治らないこともあります。その他の病型には、やや盛り上がり褐色のシミのような色素沈着型、イボのように盛り上がった疣状(ゆうじょう)型があります。
日光角化症が疑われる場合、ダーモスコピー検査(拡大鏡検査)や病理検査で診断し、症状に合わせた治療を行います。主な治療法としては、患部をメスで切除する手術療法、液体窒素を使った凍結療法、免疫調整薬(イミキモド)を用いた外用療法があります。
Bowen(ボーエン)病
ボーエン病は、皮膚の一番外側の表皮にできる前癌病変です。顔面など露出している部位だけでなく、お腹や背中などの体幹部や陰部、手足などの服に隠れた部分にも発生することが多く、60歳以上の高齢者によく見られます。痛みやかゆみの症状はなく、見た目は湿疹や日光角化症に似ています。ザラザラとした赤茶色の平らな盛り上がりで、正常な皮膚との境界ははっきりしていますが、形はいびつです。ゆっくりと進行し、5~10センチ程度まで徐々に大きくなります。
ボーエン病は表皮内がんであり、表皮に留まっている間は転移しませんが、表皮の下にある真皮層まで浸潤すると有棘細胞がんに移行する可能性があります。
原因としては、ウイルス性皮膚疾患や外傷の傷あとから発生することがあります。また、最近はまれですが、多発する場合は長期間にわたって井戸水を飲み続けることで起こるヒ素中毒が原因となることもあります。陰部などにできた場合は、ヒトパピローマウイルス感染が原因として考えられます。
ボーエン病が疑われる場合、ダーモスコピー検査や病理検査を行います。治療は初期であれば転移の心配がないため、外科的に患部を残さず切除することで根治が可能です。放置すると深く進行し、悪性度が高くなるため、早期治療が重要です。
悪性黒色腫(メラノーマ)
悪性黒色腫は、ほくろと見間違いやすい代表的な皮膚がんです。黒色の盛り上がりで、色調にムラがあり、いびつな形をしているのが特徴です。メラニン色素を作り出す色素細胞(メラノサイト)ががん化するもので、皮膚がんの中でも悪性度が高く、他の皮膚がんとは診断や取り扱いが異なる点があります。人種差があり、白人での発生が最も多く、日本人では10万人あたり1~2人とされています。
紫外線を浴びやすい顔や手足などの末端部に発症しやすく、日本人に多いのは足の裏や手のひら、爪などにできるタイプです。「ほくろのがん」とも呼ばれるように、ほくろ(母斑細胞)から生じることもあります。大きなほくろや急にできたほくろは、このがんに該当する可能性があります。悪性黒色腫はごく初期の小さなものでも、リンパ管や血管を通じて全身に転移することがあります。ほくろと区別がつきにくく、発見が遅れることも多い皮膚がんですが、悪性度が非常に高いため、できるだけ早期に発見することが重要です。
悪性黒色腫が疑われる所見
- 形が左右非対称
- 皮膚との境界がはっきりせず輪郭が不明瞭
- 色がまだらで濃淡が不均一
- 6ミリ以上の大きな病変
- 急速な増大、形状・色調・表面の状態の変化
皮膚がんは放置せず、早期治療が重要
皮膚がんであっても、転移していない表皮にとどまる初期の段階であれば、手術によって完全に摘出することで完治の可能性が高くなります。しかし、進行するとリンパ節や内臓へ転移し、浸潤も深くなります。その場合、抗がん剤治療が必要になったり、手術範囲が大きくなったりします。
そのため、皮膚がんの特徴を覚えておき、疑いがあれば早めに医療機関で診断を受け、適切な治療を受けることが重要です。
当院では、検査結果と患者様の状態に合わせた治療方法を詳しくご説明し、インフォームド・コンセントを重視して最善の治療を行います。
切除した腫瘍については、完全に取りきれているかどうかを確認しています。腫瘍の切除に伴って生じた皮膚の欠損に対しては、小範囲の場合は縫合閉鎖や皮弁術(皮膚の血流を保ちながら移植する方法)、広範囲の場合は植皮術を行います。手術方法については、腫瘍の切除範囲や整容的な面を考慮して個別に選択しています。
「できもの」などができ、皮膚がんについて不安がある方や、少しでも異変を感じた場合は、当院までお気軽にご相談ください。