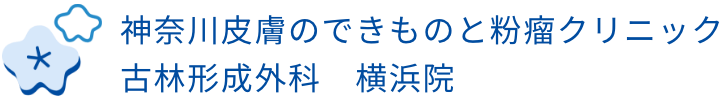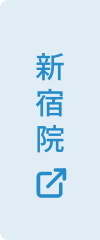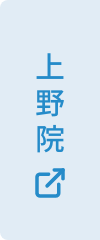メラノーマ(悪性黒色腫)の見分け方|ほくろとの違いと初期症状を解説

神奈川県横浜市の「神奈川皮膚のできものと粉瘤クリニック 古林形成外科横浜院」です。当院では、日本形成外科学会認定の形成外科専門医が、ほくろや皮膚がんの診察・治療を行っています。
本記事では、メラノーマ(悪性黒色腫)の見分け方や、ほくろとの違い、そして早期治療の重要性について解説します。ぜひご参考ください。
メラノーマ(悪性黒色腫)の見分け方とは
メラノーマ(悪性黒色腫)は、皮膚がんの一種で「ほくろのがん」とも呼ばれています。皮膚がんの中でも特に悪性度が高く、進行が早いため、早期に異常を発見して適切な治療につなげることが極めて重要です。
見た目が通常のほくろとよく似ているため、自己判断で見分けるのは難しいことがあります。しかし、特徴的な所見を参考にセルフチェックを行うことで、早期発見のきっかけになります。その代表的な方法が「ABCDEルール」です。これは、以下の5つの視点から皮膚の病変を観察する国際的な基準として広く用いられています。
ABCDEルール
A(Asymmetry:左右非対称)
通常のほくろは円形や楕円形で左右対称ですが、メラノーマは形がいびつで非対称になることがあります。
B(Border:境界)
正常なほくろは境界が明瞭ですが、メラノーマは周囲との境界が不明瞭で、ギザギザした輪郭を示すことがあります。
C(Color:色の濃淡)
通常のほくろは均一な茶色や黒色ですが、メラノーマは黒・茶・赤・白・青など複数の色が混在し、色むらが目立ちます。
D(Diameter:大きさ)
直径6ミリを超えるほくろには注意が必要です。特に短期間で急速に大きくなる場合はリスクが高まります。
E(Evolution:変化)
大きさ・色・形が急に変化したり、出血やかさぶたを繰り返す場合は、メラノーマの可能性があるため注意が必要です。
メラノーマ(悪性黒色腫)と普通のほくろとの違い

メラノーマ(悪性黒色腫)は「ほくろのがん」とも呼ばれるほど、見た目が通常のほくろに似ています。そのため、一般の方が自己判断で区別するのは容易ではありません。「ABCDEルール」にもとづくと、左右の非対称性、境界の不明瞭さ、色のむら、大きさ、そして変化といった特徴が、ほくろとの大きな違いになります。
通常のほくろは形が整って左右対称であり、境界が明瞭で色調も均一です。また、長年にわたりほとんど変化せず安定しているのが一般的です。
一方、メラノーマは形がいびつで非対称になりやすく、境界がギザギザしてぼやける傾向があります。色も黒や茶色にとどまらず、赤・白・青など複数の色が混在することがあり、大きさも6ミリを超える場合が見られます。さらに、短期間で急速に大きくなったり形が変化するなど、変動のある所見が特徴です。
つまり、「長期間変わらず安定しているか」あるいは「短期間で形や色に変化があるか」が、ほくろとメラノーマを見分けるポイントといえます。
メラノーマ(悪性黒色腫)とはどのような病気か

メラノーマ(悪性黒色腫)は皮膚がんの一種で、「ほくろのがん」とも呼ばれています。通常のほくろと見分けがつきにくいため発見が遅れやすい一方で、皮膚がんの中でも特に悪性度が高く、早期から全身に転移しやすいのが特徴です。
発生の仕組みとしては、メラニン色素をつくる細胞であるメラノサイトががん化することで生じます。病変は黒っぽい盛り上がりとして現れることが多く、色のむらや形のいびつさが特徴的です。
発症率には人種差があり、白人に多くみられるのに対し、日本人での発症は10万人あたり1〜2人程度と報告されています。ただし、日本人の場合は紫外線を浴びやすい顔や手足に加え、足の裏、手のひら、爪の下などにも発症しやすい傾向があります。既存のほくろ(母斑細胞)から発生することもあるため、大きなほくろや急に出てきた新しいほくろには注意が必要です。
メラノーマは小さな初期病変であってもリンパ管や血管を介して転移する可能性があります。そのため「ただのほくろ」と放置すると急速に進行し、治療が難しくなることがあります。少しでも疑わしい変化を感じた場合は、できるだけ早めに専門医を受診することが大切です。
ほくろとの違いを見分けるメラノーマ(悪性黒色腫)の検査

通常のほくろなのか、それともメラノーマ(悪性黒色腫)をはじめとする皮膚がんなのかを判断するためには、専門医による診断が欠かせません。
診察では、まず視診や触診を行い、病変の形、大きさ、色の濃淡、境界がはっきりしているかどうか、盛り上がりの有無、出血やかさぶたの有無などを総合的に評価します。次に「ダーモスコピー(皮膚拡大鏡)」を用いて、皮膚表面の構造や色の分布パターンを詳しく観察します。肉眼では判別しにくい特徴を捉えることができ、悪性かどうかをより高い精度で判断できます。
さらに、メラノーマが疑われ、進行している可能性がある場合には、超音波検査やCT、MRIといった画像検査を行い、リンパ節や内臓への転移の有無を確認します。最終的な確定診断には、病変の一部または全体を切除して行う病理組織検査が必要となります。
メラノーマ(悪性黒色腫)の治療法

メラノーマ(悪性黒色腫)の治療は、病気の進行度や転移の有無によって異なります。基本となるのは手術による切除であり、まず腫瘍を完全に取り除くことが第一選択となります。
手術では腫瘍の厚さに応じて、腫瘍の周囲から約5mm~20mmの範囲を含めて切除します。切除後に生じた皮膚の欠損部は、必要に応じて皮膚移植などで再建します。また、リンパ節への転移が確認された場合には、リンパ節をまとめて切除する「リンパ節郭清」を行うこともあります。
一方、手術による完全な切除が難しい場合や、すでに臓器への転移が認められる場合には、免疫チェックポイント阻害薬や分子標的薬といった薬物療法が中心となります。さらに、手術、薬物療法、放射線治療を組み合わせた集学的治療が行われることもあります。
まとめ|症状に不安を感じたら早めに専門医に相談を

メラノーマ(悪性黒色腫)は皮膚がんの一種で、「ほくろのがん」とも呼ばれます。見た目が通常のほくろとよく似ているため、自己判断で区別するのは難しい場合があります。
「ABCDEルール」を用いたセルフチェックは目安にはなりますが、実際に通常のほくろか、あるいはメラノーマを含む皮膚がんなのかを判断するには、皮膚科専門医の診断が欠かせません。
メラノーマは皮膚がんの中でも特に悪性度が高く、進行も早いため、早期発見と早期治療が極めて重要です。少しでも不安な症状や変化に気づいたら、できるだけ早めに専門医へ相談することをおすすめします。
皮膚がんの治療は当院までご相談ください

神奈川県横浜市にある「神奈川皮膚のできものと粉瘤クリニック 古林形成外科横浜院」では、日本形成外科学会認定の形成外科専門医が、皮膚がんに対して専門的な知識と経験に基づいた診断と治療を行っています。
皮膚がんは初期であれば、手術によって病変を完全に切除することで、高い確率で治癒が期待できます。しかし、進行するとリンパ節や内臓への転移、あるいは皮膚深部への浸潤リスクが高まり、より広範囲な手術や抗がん剤治療が必要となる場合があります。
気になる症状がある方や、皮膚がんではないかと不安を感じている方は、早めに当院へご相談ください。