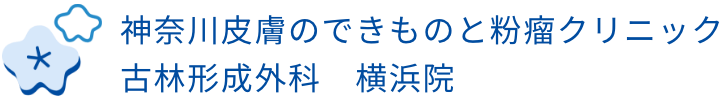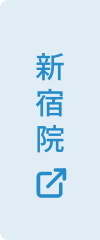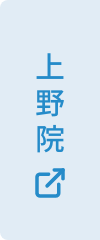できものとは
できものとは、皮膚にできるしこりや腫瘍のことを指します。
身体のあらゆる部位に生じ、種類によっては皮膚の表面にできるものや内側にできるものがあります。また、色や硬さ、大きさも様々です。
イボやニキビ、ほくろなども「できもの」の一種です。これらは多種多様で、痛みなどの自覚症状がない場合も多いですが、病変が進行すると、痛みや出血、悪臭といった症状が現れたり、大きさや見た目が変化することがあります。中には皮膚がんなどの悪性が疑われることもあるため、異変を感じたら速やかに医療機関を受診し、皮膚腫瘍の種類に応じた検査と適切な治療を受けることが重要です。
悪性腫瘍の場合はもちろん、良性のイボや粉瘤であっても、なるべく早期に手術を受けることが患者様の負担軽減につながります。
こんなお悩みがある方はぜひご相談ください
- できものがあるが悪性でないか心配
- 「ほくろ」・「イボ」がだんだん大きくなってきた
- できものから出血がある
- できものが化膿してしまった
できものの種類
粉瘤(アテローム)
粉瘤(アテローム)は、表皮嚢腫(ひょうひのうしゅ)とも呼ばれる良性の皮下腫瘍です。体表のどこにでもできますが、発症しやすいのは顔、首、背中、耳の後ろなどです。
皮膚の上皮成分が皮下に落ちて袋状の組織を形成し、その中に垢(角質)や皮脂といった老廃物が溜まることで生じます。発症の要因としてウイルス感染や外傷、体質などが考えられていますが、詳しい原因は不明です。
初期は数ミリ程度の盛り上がりで、ほとんど目立つことはなく、ニキビやしこりのように感じます。しかし、放置すると皮膚の隆起がはっきりと認識できるほど大きくなり、悪臭を放ったり、細菌感染や圧迫による炎症を引き起こしたりすることがあります。
粉瘤はニキビや吹き出物と誤認されることがありますが、ニキビのように自然治癒することはなく、手術を行わない限り根治しないという特徴があります。ご自身で内容物を押し出そうとすると、袋が破れて炎症を起こす恐れがあるだけでなく、脂肪組織内に内容物が散らばり、慢性化してしまうことがあります。無理に排出せず、早めに受診することが重要です。
脂肪腫(リポーマ)
脂肪腫(リポーマ)とは、皮下に発生する良性の腫瘍のことで、柔らかい部位にできる軟部良性腫瘍の中で最も多くみられます。
身体のどこにでも発生する可能性がありますが、背部、肩、頚部(特に後頚部)などに現れることが多く、上腕、臀部、大腿など四肢にみられることもあります。
脂肪腫は痛みやかゆみなどの症状はなく、皮膚がドーム状に盛り上がり、柔らかいしこりが認められます。大きさは数ミリ程度の小さなものから10センチ以上に及ぶものまで様々で、放置すると徐々に大きくなり、目立つことがあります。一般的に、発症には肥満や糖尿病、遺伝などが関係しているといわれていますが、現在のところこれらに明確な根拠はなく、詳しい原因は不明です。
脂肪腫は自然に治ることはなく、内服薬や外用薬で治癒することもありません。また、内容物が液体状ではないため、注射器を使って吸い出すこともできません。根治には摘出手術が必要です。
脂肪腫は大きくなると、手術や費用面で患者様の負担も大きくなってしまいます。脂肪腫自体は良性の腫瘍ですが、見た目や症状が似た悪性腫瘍もあるため、小さいしこりであっても気付いた際には放置せず、専門の医師の診察を受けることが重要です。
石灰化上皮腫(毛母腫)
毛穴の深部には、毛母(もうぼ)と呼ばれる毛を作り出す細胞があります。この細胞が石灰化を起こし、皮下に石のような硬いしこりができるのが石灰化上皮腫(せっかいかじょうひしゅ)です。
顔、首、腕などに好発する良性の皮下腫瘍で、大きさは0.5~3センチ程度のものが多く、水ぶくれ(水疱)のように見えたり、大きくなると皮膚の薄い部分では腫瘍が透過し、黄白色や青黒い色に見えたりすることもあります。
基本的には無症状ですが、しこりを押すと痛みやかゆみを伴うことがあります。また、細菌感染や異物反応を起こすことがあり、その際には痛みやかゆみが強くなり、状態によっては皮膚に穴が開いてしまうケースもあります。この場合、早急に手術を受けてきちんと除去することをおすすめします。
詳しい原因は分かっていませんが、子どもによく見られ、若干、女性に多い傾向があります。見た目が丸いため、粉瘤や脂肪のかたまりと誤認されることも多いです。
ほくろ
ほくろは良性腫瘍の一種で、表皮にメラニン色素を生成するメラノサイトが集まり、黒色斑を形成します。
隆起したもの、平らなもの、茶色(褐色)のものから黒いものまで、形状も円形や楕円など、その見た目は様々です。だれにでも1つはあり、チャーミングポイントとして挙げられるほど身近なほくろですが、まれに悪性が含まれているため、異変を伴うものには注意が必要です。
ほくろと皮膚がんの鑑別は非常に難しいため、診療においては患者様の症状や状況をじっくりと伺ったうえで検査を行います。ダーモスコピーと呼ばれる皮膚拡大鏡を用いて検査を行いますが、悪性の疑いが強くリスクが高いと判断した場合は、手術で切除し、病理検査を行うことで診断が確定します。
ご自身のほくろが皮膚がんの特徴と似ていたり、ほくろの異変に気付いたりした場合は、お早めに診断を受けることをおすすめします。
イボ
イボは、数ミリから数センチ程度の盛り上がったできもので、ウイルスや加齢など、発生原因はいくつかあり、見た目や種類も様々です。炎症を伴ったり、日常生活に支障をきたしたり、放置すると大きくなるタイプのイボもあります。大きくなると、綺麗に治すことが難しくなるため、気になるイボがある場合はお早めにご相談ください。
主なイボの種類
イボ(尋常性疣贅:しんじょうせいゆうぜい)
最も一般的なイボで、皮膚の小さな傷からヒトパピローマウイルス(HPV)が皮膚深層に感染することで発症します。通常、痛みやかゆみは伴いませんが、放置するとさらに増えたり、人にうつしたりすることがあります。形状は様々です。
水イボ(伝染性軟属腫:でんせんせいなんぞくしゅ)
ポックスウイルスの感染によって生じるイボで、6歳以下の子どもに多くみられます。胸やお腹、脇の下といった皮膚の薄い部分にできやすく、大きさは数ミリ以下がほとんどで、形状は光沢のあるドーム状です。掻くことで内容物が皮膚に付着し、次々とうつっていくため、集団生活を送っているお子さんは積極的に治療を受けることが大切です。
老人性イボ(脂漏性角化症:しろうせいかくかしょう)
紫外線による肌の加齢性変化が原因と考えられているイボで、中年以降に多くみられますが、20代で発症する方も少なくありません。顔面、頭部、胸元などにできやすく、茶色や黒ずんだ茶色に盛り上がり、類円形の腫瘤として認められます。加齢により増加しやすく、シミが隆起して老人性イボになることもよくあります。
首イボ(アクロコルドン)
非感染性である脂漏性角化症が、皮膚が薄く柔らかい首や脇の下、鼠径部などに生じると、有茎性に盛り上がった小さなイボとして現れることがあります。これを首イボ(アクロコルドン)といいます。首イボは、とくに心配なイボではありませんが、衣類で擦れたり、ねじれたりすることで痛みや炎症を起こすことがあります。
皮膚線維腫
成人女性の腕や大腿部、足に発症することが多い数ミリから2センチ程度の良性の腫瘍です。見た目は肌色から茶色(褐色)で、皮膚の表面が少し盛り上がっていることが多く、触ると皮下にやや硬いしこりが認められます。痛みやかゆみなどの自覚症状はほとんどありませんが、患部をつまむと痛みを生じたり、発症部位によっては、衣類が擦れて不快感を伴ったりすることがあります。原因は明らかになっていませんが、虫刺されや小さな傷、遺伝が関係すると考えられています。
多くは痛みなどの症状はなく、悪性化することもないため、経過観察で問題ありません。しかし、大きいものや、増加傾向にあるものは、まれにDFSP(隆起性皮膚線維肉腫)という悪性腫瘍との鑑別が必要になるため、病理検査を行います。
外骨腫(がいこつしゅ)
外骨腫(がいこつしゅ)は、原発性骨腫瘍の中で最も多いとされている良性の腫瘍です。骨幹端部(骨の端)にツノのように膨隆する骨腫瘍で、表面が軟骨で覆われており、骨軟骨腫(こつなんこつしゅ)とも呼ばれます。形成外科領域では主に前額部(おでこ)や頭蓋、爪の下によく見られます。
前額部や頭蓋では痛みはありませんが、整容面の問題で切除を希望される患者様が少なくありません。骨に生じる腫瘍ですが、基本的には手術による摘出を行います。局所麻酔下でツチとノミを使用して摘出することができ、摘出した組織は病理検査を行います。創部は形成外科的に細かく縫合し、できる限り目立たないようにします。
ガングリオン
ガングリオンは手首の関節の近くにできることが多い腫瘤です。米粒大からピンポン玉ぐらいまでの大きさで、柔らかいものから硬いものまであります。手首の関節には関節を包む関節包があり、その中は潤滑油としての働きがある滑液(かつえき)で満たされています。この滑液が何らかの理由で外へ漏れ出し、袋状の腫瘤を皮下で形成して腫れとして表皮に現れるのがガングリオンです。手首の関節に発生することが多いですが、指の付け根の腱鞘に生じることもあります。
多くの場合、強い痛みはありませんが、神経が圧迫されると痛みを感じることがあります。治療は保存療法または外科的な摘出になります。注射で内容物を吸引する穿刺吸引で再発を繰り返す場合には、手術による治療が考慮されます。
神経線維腫(しんけいせんいしゅ)
神経線維腫は、皮膚や皮下組織にできる常色~淡い紅色の柔らかい腫瘍で、大きさは様々です。ほとんどの患者様は思春期頃から少しずつできはじめ、年齢とともに増加します。単発性のものと多発性のものがあり、多発性の場合は神経線維腫症Ⅰ型(レックリングハウゼン病)の可能性が考えられます。
痛みなどの症状はなく、悪性になることもない良性の腫瘍ですが、整容的な観点から摘出することが多く、外科的な切除を行います。
神経鞘腫(しんけいしょうしゅ)
神経鞘腫は、神経の周りを覆っている神経鞘(神経のさや)から発生する良性の腫瘍で、抹消神経のシュワン細胞が元になっていることからシュワン細胞腫とも呼ばれます。多くの場合、皮下組織や筋肉のような軟部組織に発生しますが、脳や脊髄、消化管などに発生することもあります。
発生部位によって症状は異なりますが、皮下にできると圧迫によって痛みを伴うことがあるため、外科的治療が検討されます。大きな神経の場合、術後に神経障害が起こることがあるため、より慎重な手術が求められます。
脂腺母斑(しせんぼはん)
脂腺母斑は、先天性の皮膚奇形で、黄色のあざに見えることが多く、頭部にできやすい傾向があります。初期は皮膚とほぼ同色であるため見分けがつきにくいですが、頭部にあると脱毛斑に見えます。表面はザラザラすることが多いですが、平坦な場合もあります。
思春期くらいになると大きくなりはじめ、あざがイボ状になります。成人(30歳)以降になると、まれに腫瘍となり悪性化することがあるため、通常、小中学生以降での切除が考慮されます。
表皮母斑(ひょうひぼはん)
表皮母斑は、出生時または生後2~3か月頃からみられる表皮の過形成による「あざ」です。新生児の1000人に約1人の確率で発生するといわれていますが、原因は不明です。表面がザラザラとした褐色のあざで、頚部や胴体、手足に現れることが多く、帯状に細長く広がって存在します。自然消退することはなく、徐々に母斑の範囲も大きくなりますので、治療の適応となります。手術による切除か、メスで表皮を浅く削り取る治療を行うことがあります。
悪性のできものには要注意
「できもの」には、良性腫瘍だけではなく悪性腫瘍も含まれるため、注意が必要です。
良性のものとの見分け方には、硬さや表面の状態がポイントとなりますが、完全に見極めるには専門医の診断が必須です。自己判断をせず、必ず受診してください。
「できもの」について気になる方や不安のある方は、以下の詳細ページならびに当院までお気軽にお問い合わせください。